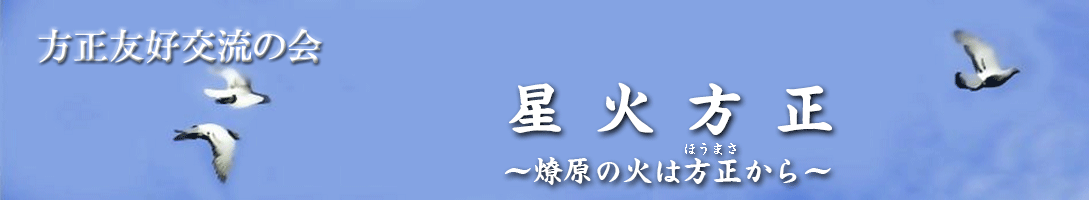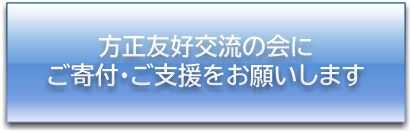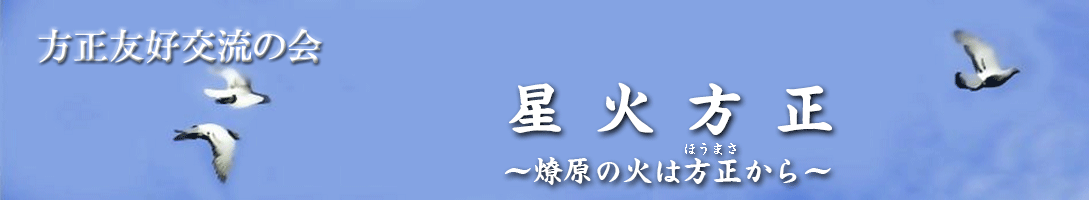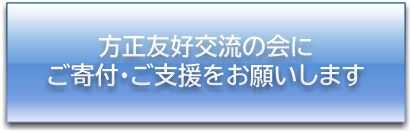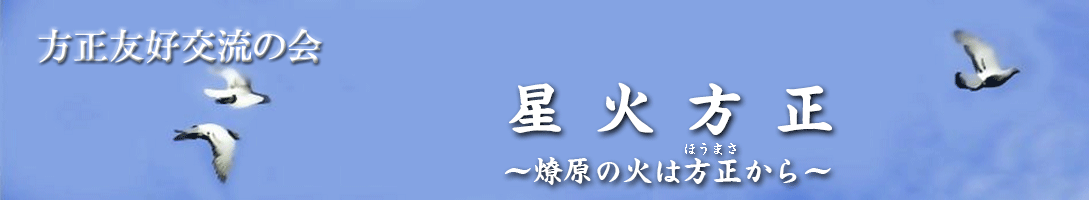 |
|
トップ |
会報『星火方正』 |
イベント&お知らせ |
規約・役員 |
関連書籍 |
入会案内
|
|
第39号(2024年12月発行) / 1冊 の 13記事 を表示しています。
- 皆さん、ありがとうございました1
- 大類善啓
- 本号も、皆さまの貴重な会費とあたたかいカンパで発行することができました。改めて御礼を申し上げます。ご寄稿いただいた方々、新聞記事をお送りいただいた方々、ありがとうございました。 /// 続きは本誌ご参照
- 元日本兵の父・黒井慶次郎の蛮行を父の初任地・中国公主嶺で謝罪しました2
- 黒井 秋夫
- 2024 年11 月3 日(日)午前10:00 雨上がりの晴天、やや寒い。山形県櫛引町東荒屋(現・鶴岡市)赤川の土手脇にある黒井家のお墓に眠る父・黒井慶次郎に中国吉林省公主嶺で中国の皆さんに謝罪できたことを報告しました。20 歳で招集された初任地、公主嶺。一時は20 万人の関東軍が駐屯したという。独立守備隊に配属された父は南満州鉄道周辺の「匪賊討伐」を戦った。周囲の村を襲いどれほどの中国人を殺したか息子の私は分からない。何をしたかは一言も言わずにあの世に逝った。 /// 続きは本誌ご参照
- 78年ぶりの葫蘆島と王希奇画伯のアトリエ訪問5
- 戸塚章介
- 日中友好協会東京都連が企画した「葫蘆島から瀋陽へ」引き揚げの足跡を訪ねる旅に参加して中国東北部(旧満州)へ行ってきた。旧満州へは90年代から数回訪れているが、大連、瀋陽、長春、哈爾濱などの旧満鉄沿線が中心だった。今回渤海湾に面した葫蘆島を訪問するというので高齢を心配しながらツアーに参加した。葫蘆島は1946年から48年にかけて日本人居留民105万人が日本へ向けて船出した引き揚げ港である。筆者も9歳で一家6人とともにここから帰国した。言わば私のルーツでもある。 /// 続きは本誌ご参照
- 「満洲の歴史を語り継ぐ高知の会」について8
- 﨑山ひろみ
- 2013年から県立高知城歴史博物館館長や大学教授などと私が、満洲体験をしてきた人たちの体験の聞き取りをしてきましたが、DVD他、資料なども60人分以上が保管されていて「なんとかこれを多くの人に伝えたい」と2018年に実行委員会を立ち上げ、話し合いがなされました。9月に規約を作り、「満洲の歴史を語り継ぐ高知の会」を立ち上げ、年に1~2回講演会や学習会を開くことにしました。 /// 続きは本誌ご参照
- 日本の部落解放運動と天皇制―西光万吉と槙村浩における天皇制認識の差異12
- 山口直樹
- 水平社の創設者の一人、西光万吉は、1895年4月17日に父、清原道隆、母コノエの長男として生まれている。本名を清原一隆といった。父親は橿原市の善光寺で1850年に生まれ明治維新のころには西光寺に入寺していたという。 /// 続きは本誌ご参照
- イスラエル・ウクライナ ただちに停戦、武器送るな 熱核戦争阻止・人類生存が最優先21
- 星野郁夫
- 世界のリーダーたちは、人間自らが人類生存の危機をつくっていることに気付いてほしい。いま人類は、生存の危機にある。地球環境は言うに及ばず、熱核戦争ぼっ発の危機は日ごとに増している。世界は、アメリカ一極支配が終わり、世界の、秩序とルールが壊れ、果てしないルールなき闘いと競争の時代に入った。1991年のソ連邦解体は、当時の冷戦終結とデタント(緊張緩和)の始まりではなかったのか。デタントは、米ソ両超大国の合意と理解が前提のはずだったが、いまや真逆の展開になっている。ソ連とワルシャワ条約機構は解体し、ヨーロッパにおいて社会主義国の協力協同は、この世に存在しない。あるのは、アメリカ一極支配とNATOだけだ。 /// 続きは本誌ご参照
- 『「満蒙開拓民」の悲劇を超えて』(大類善啓編著・批評社)を読んで25
- 滝永登
- 本書刊行のいきさつについては、編著者である大類善啓さん自身が記した本書の「はじめに」と「あとがき」とによって知ることができる。本誌『星火方正』の読者であれば、「方正地区日本人公墓」の存在と建立に至る経緯については大筋既知のことと思う(私自身も)。さらに、この同じ場所には「麻山地区日本人公墓」、「中国養父母公墓」、「藤原長作記念碑」があることを知る人となるといくぶん人数は減るのだろうか(私もその一人)。 /// 続きは本誌ご参照
- 忘れてはいけない!中国の民衆の中で深く絆を結んだ人々―「『満蒙開拓民』の悲劇を超えて」を上梓して思うこと28
- 大類善啓
転載元:国際善隣協会『善隣』(2024年7月号)
- 私が中国に本当に関心を持ったというか、我が内なる心から、好奇心が沸き起こるように中国に興味を持ったのは一九七一年、キッシンジャーの極秘訪中が明らかになった時だった。当時私は、男性サラリーマンを読者対象とし、売り上げトップを誇る勢いにあった週刊誌の記者だった。 /// 続きは本誌ご参照
- 本の紹介:『戦中戦後・母子の記録』(全10巻、笠原政江編集、自家本)38
- 松岡勲
- 表題の本は、1978~1980年に京都市山科に住む笠原政江さんを中心に編集発行された全10巻の自家本(非売品)である。第6巻よりは朝日新聞社事業開発本部が編集に参加している。当時、各地の図書館に寄贈されていて、私は第1巻を茨木市(大阪府)の図書館で、第2巻を大阪府立図書館で借りて読んだ。全巻見るためには、国会図書館デジタルコレクションで読むことができる。 /// 続きは本誌ご参照
- 騙された者の責任とは…―『いのち輝け 二度とない人生だから』を上梓して41
- 蓼沼紘明
- 私は、1943年9月に元満州国東安省勃利県大茄子(現在は黒竜江省七台河市)にあった満蒙開拓青年義勇隊の訓練所の宿舎で生まれました。義勇隊の幹部だった父は翌年徴兵され、私は母に抱かれて1944年3月に帰国することができました。 /// 続きは本誌ご参照
- 『満州、少国民の戦記』を上梓して44
- 藤原作弥
- 「夏が来れば思い出す。はるかな尾瀬、遠い空―」。江間章子作詞、中田喜直作曲の「夏の思い出」は名曲だが、私が思い出すのは季節の風物詩ではなく、“あの戦争”である。私の満州体験についてはかつて書いたこともあるので「またか」と思われる読者にはゴメンナサイ。79年前、敗戦の年から一年有余、難民生活を送った中国・安東(現・丹東)での生活は満8歳の少年にとってショックの連続だった。 /// 続きは本誌ご参照
- 『回想録』を執筆して46
- 和田学
- 漸く涼しくなりました。皆様は如何お過ごしでしょうか?私は千葉県柏市在住、中国からの帰国者2世です。1972年日中国交回復した翌年、1973年11月に母(和田富美子)の34年ぶりの帰国に伴って来日してから50年になりました。この度、私の来日50年を契機に回想録を書きました。 /// 続きは本誌ご参照
- 方正日本人公墓が私たちに問いかけるものとは―「方正友好交流の会」へのお誘い93
- 方正友好交流の会
- 1945年の夏、ソ連参戦に続く日本の敗戦は、旧満洲の「開拓団」の人々を奈落の底に突き落としました。人々は難民、流浪の民と化し、真冬の酷寒のなか、飢えと疫病によって多くの人たちがハルピン市郊外の方正の地で息絶えました。それから数年後、累々たる白骨の山を見た残留婦人の松田ちゑさんは方正県政府に、「自分たちで埋葬したいので許可してください」とお願いしました。その願いは方正県政府から黒竜江省政府を経て中央へ、そして周恩来総理のもとまでいき、「方正地区日本人公墓」が建立されました。 /// 続きは本誌ご参照
|
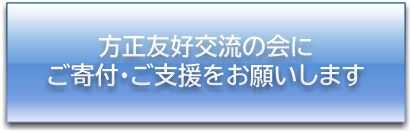
|
|
トップ |
会報『星火方正』 |
イベント&お知らせ |
規約・役員 |
関連書籍 |
入会案内
|
|
「方正友好交流の会」事務局
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6 日本分譲住宅会館4F 一般社団法人日中科学技術文化センター内
Tel: 03-3295-0411 Fax: 03-3295-0400 E-mail: ohrui@jcst.or.jp
|